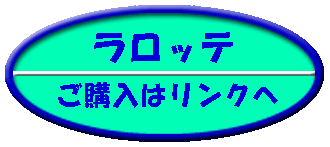

うどん粉病
若い葉や茎の表面にうどん粉をまぶしたように白いカビが一面に生えます。生きた植物にしか寄生せず、枯死した植物には寄生することができません。
春から秋にかけて発生しますが、植物によっては1年中悩まされるものもあります。
白絹病
茎や土壌の表面に白く網状のカビが生えます。この菌は、土壌に残り他の植物に感染することもあります。
夏の暑い日、風通しや水はけの悪いところに発生します。
灰色カビ病
花弁・蕾や茎葉などが、はじめは白や赤色の斑点ができ、徐々に進行して褐色や灰色のカビになります。うどん粉病と違い、枯死した植物にも寄生するため、広範囲の病気です。
春先から梅雨にかけて、さらには秋から冬にかけても発生します。
モザイク病
葉や花にモザイク状のしみを作ります。アブラムシによる伝染がこの病気の特徴です。
黒星病
葉に黒い円形の斑紋ができ、落葉して株が衰えます。バラに多く見られるのがこの病気の特徴です。
褐斑病
葉に小さな淡褐色の斑点があらわれ、徐々に進行して黒色になり、枯れた部分が広がります。炭そ病
葉・茎・花・果実などが円形の病斑ができ、葉は穴があき、果実は腐り落ちます。べと病
葉の表面に汚れたような不規則な紋が生じ、広がります。湿度の高い風通りの悪いところで発生します。
斑点病
葉に褐色の小さな斑点状の病斑ができ、生育不良や落葉の原因になります。菌核病
地際の茎が水浸し状に変色し、腐敗してやがて枯死します。20度以下の低温に発生することがあります。
さび病
葉に小さなイボ状のものができ、やがて薄皮が破れ中からさびに似た粉が飛び散ります。風通しの悪いところで発生します。
白さび病と黒さび病の2つがあります。
もち病
葉が餅を焼いたように膨れ、やがて黒褐色となり腐敗します。赤星病
葉の裏に毛ばだった丸い病斑ができ、変形しながら枯死します。春から夏にかけて発生します。
軟腐病
地際部分が腐敗し、悪臭を放ちます。細菌による病気です。
ブラウンパッチ
芝生の病気ではじめはリング状の症状があらわれ、徐々に枯れていきます。梅雨の時期に多く発生します。
苗立枯病
発芽・定植・生育初期に茎の地際からくびれて倒伏します。土壌伝染性の病気なので、土壌の管理をしっかりとしましょう。
疫病
灰緑色の油がにじんだような病斑ができ、葉はたれ下がり枯れます。縮葉病
葉が異常に膨らみ淡緑色や紅色に変色し、縮んで奇形になります。春に発生します。


