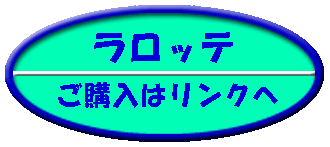

アブラムシ
アブラムシは、ウイルス病の媒介をしたり、蟻を誘う分泌物を出します。いろいろな種類がおり、さまざまな植物に害を与えます。
媒介によるウイルス病には、モザイク病、萎縮病、黄斑えそ病、軟腐病などがあります。
発生が多い時期は、夏の初めと秋になり、真夏はやや弱まります。
カイガラムシ
果樹や庭木、花木などの枝や草花の根に寄生したりします。寄生された植物は、生長が阻害され枝枯れを起こします。
また、カイガラムシの糞(排泄物)によってスス病やこうやく病になる恐れも出てきます。
成虫は、殻に覆われているため、薬剤の効きがあまり期待できません。
そのため、卵がふ化する春先から夏までの成虫になりきれていない幼虫の内に駆除します。
ハダニ
葉や花に小さな白い斑点ができます。高温や乾燥を好み、春から秋まで発生し、夏場が最も活動が活発です。
繁殖力が強く、薬剤の抵抗力もあるため、予防には複数の薬剤が必要になります。
ヨトウムシ
夜行性で葉や花、茎を食べてしまいます。発生は、春から秋まで年に2回発生するものもいれば、年5回発生するものもいます。
蝶や蛾は、自由に飛んできて卵を産みつけるため、防ぐには寒冷紗や防虫ネットが必要になります。
アザミウマ
葉や花に寄生して吸汁します。被害がすすむと奇形花や花が咲かないなくなります。
夏場に被害が多くなります。
コナジラミ
多くの草花、野菜に寄生し、ハダニと同じような被害が出ます。温室やフレームの普及と共に多発する害虫です。
ケムシ
蝶や蛾の幼虫で主に葉を食害し、種類により年に数回発生する厄介な害虫です。毒があるものもいるため、取り除くときには、素手で行わないようにしましょう。
ハバチ
外見はケムシと同じように見えますが、ハチの仲間の幼虫です。大発生して葉を食い尽くすことがあるので注意が必要です。
コガネムシ
成虫は、果樹や草花などの葉を食べ、幼虫は、土中で根を食害します。成虫は、定期的に薬剤散布を行い、幼虫は、植物を植える前に予防しましょう。
ネキリムシ
主に苗の地際部の茎が切断されます。昼間は、土中にいるために駆除が難しい害虫です。
エカキムシ
葉の中に入り込み、葉を食害しながら移動をする害虫です。被害にあった葉は、白く絵を描いたような跡が残ります。
ナメクジ
昼間は、鉢底などの物陰に隠れていて、雨上がりや夕方に活動しはじめます。花弁や若い葉、果実などに食害を与えます。
光沢のある白い粘液の這った跡があり、不快な気持ちになります。
ダンゴムシ
触れると体を丸めるダンゴムシと体を丸められないワラジムシ。花壇のレンガ、岩や石の下にかたまって生息します。
ダンゴムシは、植物の茎や葉、根などを食害しますが、ワラジムシは直接的な被害はないです。
ムカデ
よく農作業で土をいじっていると見かける虫です。植物に直接的な被害はないです。
噛まれると激痛と共に噛まれた患部が腫れることがあります。
作業の邪魔になりますし、不快な気持ちになるので駆除しましょう。
アリ
植物に直接的な被害はないものの、害虫のアブラムシを助けたり、いろいろと邪魔をしてくれます。土を掘り巣を作るため、根の生長を妨げます。
見かけたらすぐに駆除をしましょう。


